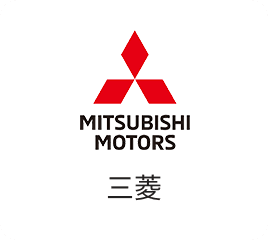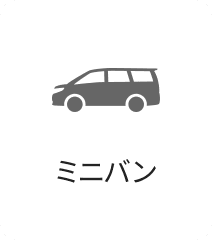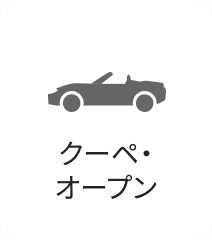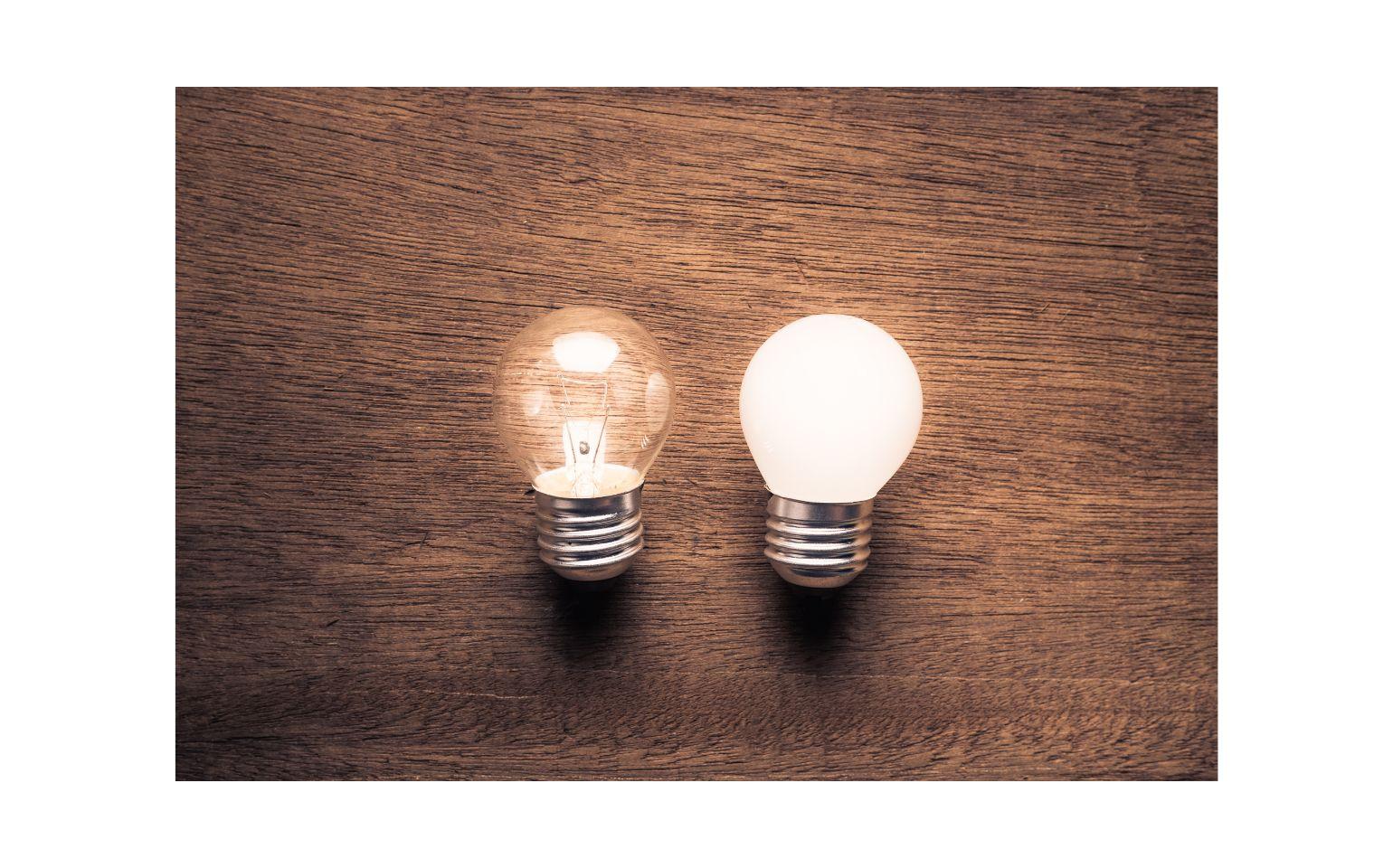若者の「車離れ」はなぜ起こる?背景と本当の理由を探る
更新日:2025.06.23
「昔は若者の憧れだった車が、今では“無くても困らないもの”になった」。
そんな声が聞かれるようになったのは、いつからなのでしょうか。
実際に、免許を取らない若者や車を所有しない若年層が増加しているのは確かです。
しかし、それは「車が嫌いだから」ではなく、むしろ時代の変化や生活の多様化に理由があるのかもしれません。
この記事では、その背景にあるリアルな事情について掘り下げていきます。
【車に興味はないけど、移動手段として必要な方へおすすめなカーリース】
車のことはよく分からないけれど、移動手段として必要となるときもありますよね。
そんな方へおすすめなのが、カーリースです。
しかし、カーリースが気になっているもののネット上での契約に不安を感じる方も少なくありません。
カーリースに対して不安があって利用を踏みとどまっている方。
ぜひ、出光興産のカーリース「ポチモ」にお任せください!
ポチモは納車後30日間、外装修理に無料で対応いたします。
「サイトには記載されてなかったキズがあった」という、万が一のトラブルもポチモなら全プランで対応!
お時間あれば、ぜひ下記ページからポチモについてご覧ください。
\安心の出光提供クオリティ/
ポチモについて見てみる経済的な問題だけではない
都市部の交通事情や生活スタイルの変化が影響
統計で見る若者の「車離れ」現象
若者の車離れが進んでいる、と言われるようになったのには明確なデータの裏付けがあります。
ここでは、運転免許の取得状況や新車の購入数など、実際の数字からその傾向を見ていきましょう。
免許取得者の推移と年齢層別データ
かつては18歳になるとすぐに免許を取るというのが一般的でした。しかし、近年ではその流れに明らかな変化が見られます。
警察庁のデータによると、20代の運転免許保有率はこの10年で減少傾向にあります。
特に都市部では、車を持たないことへの抵抗感が少なくなってきているようです。
例えば、東京都内に住む大学生や新社会人の中には、「そもそも車を運転する機会がない」「必要性を感じない」と話す人も少なくありません。
免許を持っていないことが珍しくない環境が当たり前になっているのです。
新車販売台数から見る所有率の変化
日本自動車販売協会連合会の調査によれば、新車の購入者層は年々高齢化しており、若年層の購入割合が明らかに下がっています。
2000年代初頭と比較すると、20代・30代による新車購入は大きく減少しており、現在は40代以上が中心になっています。
この背景には、経済的な事情だけでなく、ライフスタイルや価値観の変化も影響しています。「車を買うくらいなら、その分を旅行や趣味に使いたい」という声も多く、所有を目的としない若者の消費行動が見えてきます。
経済的な理由だけじゃない現代の課題
若者の車離れについて語る際、真っ先に挙げられるのが「経済的な負担」です。
もちろん、車の購入費用や維持費は若者にとって大きな出費となるのは間違いありません。
しかし、問題はそれだけにとどまらないようです。ここでは、より広い視点から車離れの背景を探っていきましょう。
維持費・駐車場代などのコスト問題
車を所有するというのは、単に本体価格を払えば済む話ではありません。
ガソリン代、自動車税、保険料、車検代、そして都市部では特に高額になりがちな駐車場代──。これらすべてを含めると、年間数十万円の負担になることも珍しくありません。
例えば、都心に住む社会人1年目のケースを考えてみましょう。
家賃や生活費に加え、これほどの維持費を捻出するのは現実的とは言えません。そのため、「必要性が低いなら、持たないほうが合理的」と考えるのはごく自然なことなのです。
非正規雇用や低所得が影響する背景
もう一つ見逃せないのが、雇用環境の変化です。
かつては新卒で正社員として就職し、安定した収入を得ながらローンで車を購入する──そんなライフモデルが一般的でした。
しかし、今では非正規雇用の割合が増え、正社員でも昇給やボーナスが期待しづらいという声も多く聞かれます。
収入が不安定で将来が見通せない中、高額な買い物である車を「今すぐ必要」とは感じにくいのかもしれません。
車の購入はある種の「余裕の象徴」だった時代から、現実的な選択肢の一つに過ぎないものへと変わってきているのです。
都市部では「車を持たない」合理性
車離れという言葉には、どこか否定的な響きがあるかもしれません。
しかし、都市部に住む若者にとっては、車を持たないことが必ずしも「離れ」ではなく、むしろ理にかなった選択である場合も多いのです。
ここでは、交通環境や社会の仕組みに注目し、都市部の若者が車を選ばない理由を掘り下げてみましょう。
公共交通機関の発達と利便性
東京都や大阪市などの大都市では、鉄道・バス・地下鉄が網の目のように張り巡らされています。日常の移動であれば、これらの公共交通機関だけで十分に事足りるのです。
加えて、通勤・通学の時間帯には本数も多く、時間的な効率も高いのが特徴です。
また、駅やバス停から目的地までが近く、徒歩圏内で生活が完結するエリアも多く存在します。
こうした環境の中で育った若者たちにとって、「車がないと困る」という感覚そのものが希薄になっているのかもしれません。
シェアリングエコノミーの台頭
もうひとつ、都市部の車不要論を後押ししているのが「カーシェア」や「ライドシェア」といった新たな交通サービスの存在です。
必要なときにだけ車を利用できるこの仕組みは、所有の負担を軽減しつつ利便性を確保できるという点で、若者にとって非常に魅力的です。
「月に1〜2回、友人とドライブするだけなら、カーシェアで十分」──そんな声も少なくありません。必要最小限のコストで車を使える時代において、「常に持っておく必要はない」という考え方が自然と浸透してきたのです。
若者の価値観が変わった?
経済的な事情や交通インフラの充実だけでは説明しきれないのが、若者たちの「車に対する価値観」の変化です。単に持てないからではなく、「持ちたくない」「特に魅力を感じない」とする声も増えています。ここでは、そうした内面的な理由に焦点を当てていきます。
「所有すること」への価値低下
かつて車は「ステータスの象徴」として捉えられていました。
高級車に乗ることが成功の証であり、自己表現の手段でもあったのです。
しかし、現在の若者は、所有すること自体にあまり価値を見出さない傾向があります。
たとえば、音楽や映画は「CDやDVDを買う」のではなく「サブスクで聴く・観る」もの。
洋服や家電でさえ、レンタルやリセールを前提とするライフスタイルが当たり前になってきました。こうした「所有から利用へ」という考え方は、車にも自然と当てはまっていくのです。
SNSや趣味への優先度の変化
もうひとつ興味深いのが、「車にお金を使うよりも、別の楽しみに使いたい」と考える若者が多いという点です。SNSの発達により、旅行やカフェ巡り、ゲーム、推し活など、興味の対象が多様化しており、「車を買って維持する」という選択が後回しになっているのです。
加えて、SNS映えや話題性を重視する文化の中では、車そのものよりも「体験」のほうが重要視されがちです。「友人とシェアカーで出かけたほうが話題になる」「車よりスマホに課金したい」──そんな価値観の変化が、所有を遠ざけている理由のひとつといえるでしょう。
地方における車の必要性は変わらず?
都市部の若者にとって「車は不要」という選択が現実的である一方で、地方に住む人々にとっては、車は今も生活に欠かせない存在です。
では、地方の若者にとって車とはどういう存在なのでしょうか?この章では、地域による事情の違いに目を向けてみます。
移動手段としての重要性
地方では、電車やバスの本数が少なく、駅やバス停までの距離も遠いというケースが珍しくありません。
そのため、通勤・通学、買い物、通院など、日常のあらゆる場面で車が欠かせない存在となっています。特に、家族やパートナーとの生活を考えると、車を1人1台所有することが前提になっている地域もあります。
「車がなければ外に出られない」「スーパーが遠いから車で行かないと買い物できない」──こうした生活環境では、車の所有は「選択」ではなく「必須」なのです。
地方と都市のギャップとは
地方でも若者の収入が十分でないケースは多いものの、「持たざるを得ない」という事情があるため、都市部の若者と比べて車を所有する割合は高めです。ただし、彼らが積極的に車を楽しんでいるかというと、そうでもない場合があります。
維持費の負担は地方でも同じく大きく、家計を圧迫していることも多いのが現実です。それでも「生活のために必要だから」という理由で、仕方なく持っているという人も少なくありません。このあたりに、地方と都市の間での車に対する感覚のズレがあるのかもしれません。
自動車業界の今後の課題と対策
若者の車離れが進む中、自動車業界も大きな転換期を迎えています。売れなくなった理由を分析するだけでなく、これからの時代に合わせた新しい戦略が求められています。
ここでは、自動車メーカーや関連業界が直面する課題と、その解決に向けた取り組みを紹介します。
若者へのマーケティング戦略の転換
かつてのような「高性能」「高級感」を前面に出した宣伝では、若者の心をつかむのが難しくなってきました。
代わりに注目されているのが、「使いやすさ」や「環境への配慮」「ライフスタイルとの親和性」といった価値です。
たとえば、音楽好きの若者向けにスピーカー性能を強化したモデルや、キャンプ需要に対応したアウトドア仕様の車など、趣味や個性に寄り添う商品展開が進められています。加えて、SNS映えを意識したデザインやプロモーションも増えてきており、「共感」を重視したマーケティングが主流になりつつあります。
カーシェアやサブスクモデルの可能性
「買う」から「使う」へという流れの中で、カーシェアリングや車のサブスクリプションモデルは大きな注目を集めています。必要なときに必要なだけ車を使える仕組みは、特に都市部の若者にとって非常に現実的な選択肢です。
さらに、近年では定額制で車を借りられるサブスク型サービスも登場し、車を「所有せずに楽しむ」スタイルが広がっています。これにより、車のある生活の魅力を手軽に体験できるようになり、若者の興味を引き戻すきっかけにもなっているのです。
自動車業界にとっては、単に車を「売る」のではなく、「使い方」を提案する時代が到来しているのかもしれません。
まとめ
若者の車離れは、単なる「流行」ではなく、社会構造や価値観の変化が複雑に絡み合った結果といえます。経済的な事情に加えて、都市部の交通インフラの発達、シェアリングサービスの普及、そして「所有」に対する価値観の変化。これらが合わさって、車を「持たない選択」がごく自然なものとして受け入れられてきました。
一方で、地方では車が依然として生活に不可欠であることもまた事実です。つまり、車に対するニーズや重要度は、住む場所やライフスタイルによって大きく異なるのです。
これからの時代、自動車業界は「売ること」だけでなく、「どう使ってもらうか」を見つめ直す必要があるでしょう。車が再び若者にとって魅力的な存在となるためには、時代に合った価値提案が求められているのです。
\月々定額/
よくあるご質問
Q
若者の車離れは本当に進んでいるのですか?
はい、統計データからも明らかになっています。特に20代の免許取得率や新車購入率の低下は顕著で、車を所有しない若者が増えています。
Q
それでも車が好きな若者はいますか?
もちろんです。車に強い憧れや興味を持っている若者も一定数います。ただし、「買って所有する」よりも「一時的に楽しむ」といったスタイルにシフトしているケースが多いようです。
Q
車を所有するメリットはもうないのでしょうか?
そんなことはありません。特に地方では日常生活の移動手段として不可欠ですし、自由に遠出ができる点や、自分だけの空間が持てるという利点もあります。ライフスタイル次第で、所有の価値は十分にあります。