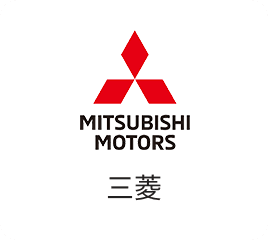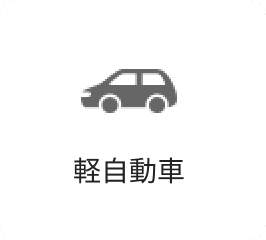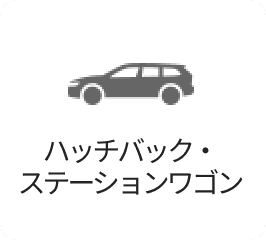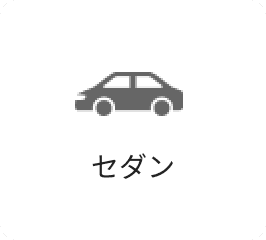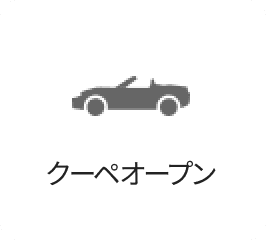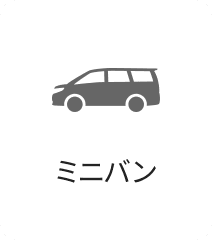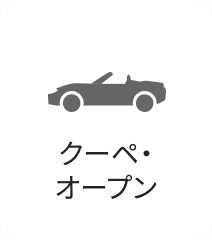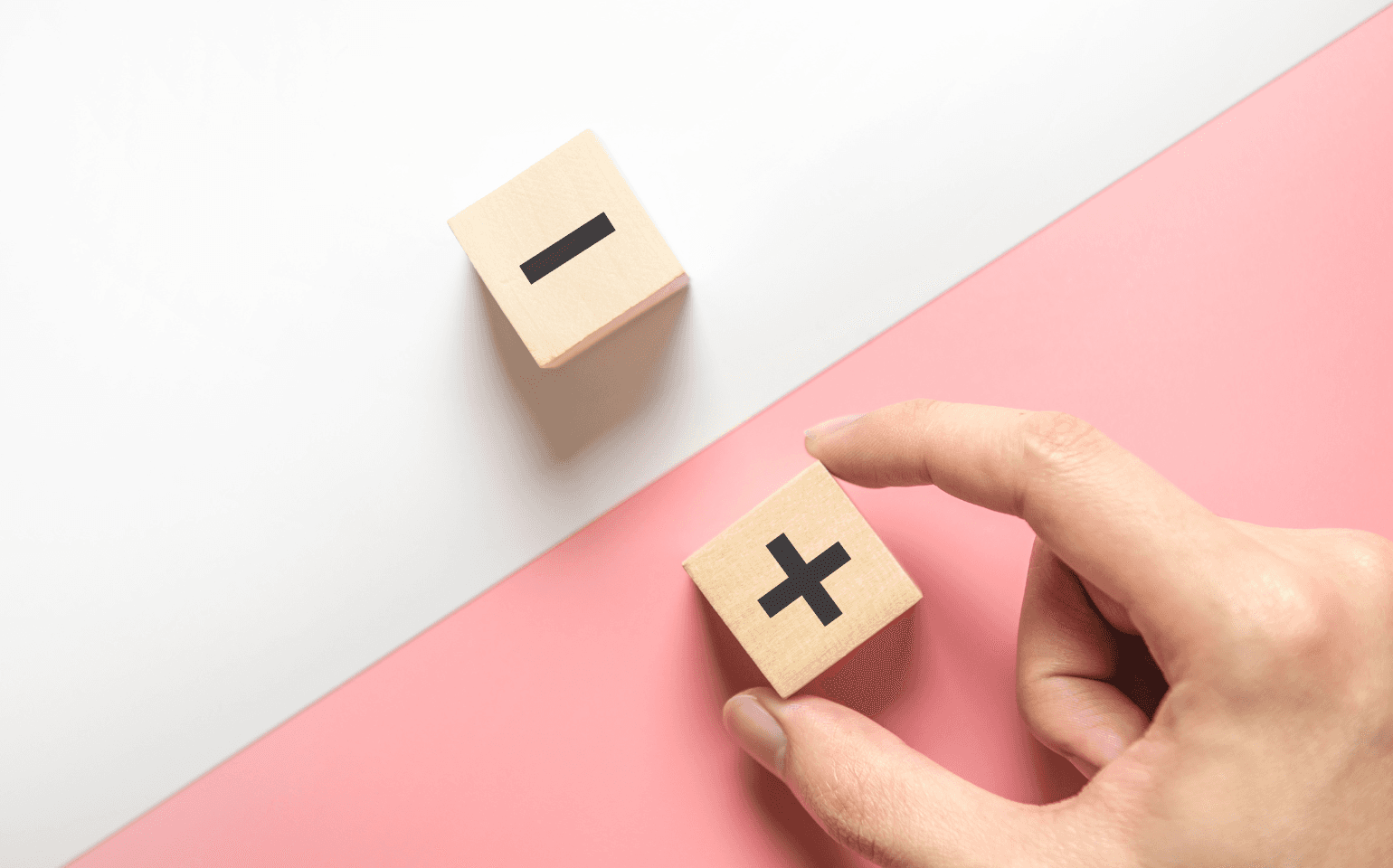ハイブリッド車のデメリットや向かない人の特徴とは?やめた方がいい、買ってはいけないと言われる理由
更新日:2025.10.28
ハイブリッド車は、「静かで燃費がいい」「環境にも配慮されている」として多くの人に選ばれていますが、すべてのドライバーにぴったり合う車ではありません。
ハイブリッド車は長距離運転で真価を発揮します。
そのため日常的に短距離走行が多かったり、運転頻度がそもそも少なかったりする人はあまり恩恵が感じられず「やめとけば良かった」と後悔しがちです。
こうして後悔する人は少なくなく、そのため「ハイブリッド車は買ってはいけない」「やめておけ」などのネガティブな口コミが散見されるようになってしまいました。
そこで今回はハイブリッド車の購入を検討している方へ向け、購入後に後悔しないために「ハイブリッド車が向かない人」の特徴を3つに分けて詳しくご紹介しながら、それぞれに適した車の選び方についても触れていきます。
検討中の方はぜひ、後悔しない選択をするための参考にしてみてください。
【ハイブリッド車の購入を検討中の方へおすすめしたい新たなマイカーの持ち方】
憧れのマイカー、購入するのも良いですがカーリースという選択肢もおすすめです。
カーリースは毎月定額の料金を支払うだけで、好きな車に乗ることができるサービス。
料金には車検費用や保険料などの一部維持費も含まれるため、まとまった出費は不要なのです!
さて、カーリースについて少しでも知っている方なら「でもカーリースって結局自分の車にならないでしょ?」とお考えかもしれませんね。
たしかに、多くのカーリースでは契約満了後に車を返却しなければなりません。
お金を支払ってきたのに、手元に何も残らないなんて!とカーリースを避けていた方も少なくないでしょう。
しかしご安心ください!
出光興産のカーリース「ポチモ」は、車の返却が不要。最後はかならず車が名実ともにあなたのものに!
ガソリン代の値引きやお近くのアポロステーションでのメンテナンスなど、出光提供ならではの特典もございます。
試しに、気になる車を探してみませんか?
頭金ゼロのカーリース
ポチモで好きな車を見つけるハイブリッド車は短距離メインの運転や走行頻度が低い人、運転を楽しみたい人などには不向き
車の性能だけに目を向けるのでなく、自分のライフスタイルとのすり合わせが大切
ハイブリッド車が向かない人とは?まず知っておくべき前提
環境への配慮、燃費の良さ、静かな走行音──こうしたハイブリッド車の魅力に惹かれて購入を検討する方は多いでしょう。
確かに、ガソリン車に比べてエコで経済的な側面があるのは事実です。
しかし、そのメリットがすべての人にとって「得になる」とは限りません。
実は、使い方によっては逆にコストがかさむこともあれば、運転していてストレスを感じることさえあるのです。
たとえば、燃費の良さはあくまで「一定の条件下」で最大限に発揮されるもの。その条件に当てはまらない場合は、期待通りの結果が得られないケースもあります。
車を選ぶ際は「一般的なメリット」よりも「自分の使い方との相性」が重要です。次の見出しでは、まさにその“相性”についてもう少し深掘りしていきます。
向き不向きは「ライフスタイル次第」で変わる
同じ車でも、人によって「快適」と感じるか「不便」と感じるかはまったく異なります。
ハイブリッド車がベストな選択となる人もいれば、そうでない人もいるのです。
たとえば、毎日長距離通勤する人にとっては燃費の良さが大きなメリットになりますが、週末にしか乗らない人にとってはむしろ維持費が気になる存在になるかもしれません。
また、都市部でのストップ&ゴーが多い運転と、田舎道でのスムーズな走行でも、バッテリーの使われ方が変わってきます。
走行環境や使用頻度、そして運転へのこだわりなど、さまざまな要素が「向き不向き」を決める材料になるのです。
では、具体的にどんな人がハイブリッド車に向いていないのか。次の章から、代表的な3つのタイプについて順に見ていきましょう。
短距離走行や運転頻度が少ない人はハイブリッド車に向いてない
ハイブリッド車は、ガソリンエンジンと電気モーターを組み合わせることで燃費効率を高める仕組みになっています。
ハイブリッド車の特性がもっとも活かされるのは、「走行距離が長い」または「日常的に運転する機会が多い」場合です。
エンジンがある程度温まり、モーターとエンジンの切り替えがうまく機能する状況でこそ、ハイブリッドの良さは際立ちます。逆に、近所への買い物や週に1〜2回の短距離運転が中心だと、エンジンが十分に暖まる前に目的地に着いてしまい、燃費向上の恩恵を受けにくくなってしまうのです。
その結果、思っていたほど燃費が伸びなかったり、ガソリン車とほとんど差がない、ということも。
たとえば片道3kmのスーパーへ毎日行くような使い方だと、ハイブリッド車の強みを発揮しきれないかもしれません。
デメリット:バッテリーの劣化スピードが早まる可能性が高い
もうひとつ注意したいのが、電気モーターを動かすための「バッテリー」の管理です。ハイブリッド車に搭載されている駆動用バッテリーは、頻繁に充放電を繰り返すことで性能を維持しやすくなっています。
しかし、短距離しか走らず、運転頻度も少ないと、バッテリーの稼働時間が減るため、劣化が進行しやすくなる場合があります。これは、スマートフォンを長期間放置したときにバッテリーが弱ってしまうのと似た現象です。
さらに、バッテリーの劣化が進むと、モーターのアシストが弱まり、加速や燃費にも影響が出ることがあります。
その結果、せっかくのハイブリッド車であっても「電気の力を感じない」といった残念な印象になってしまうことも。
つまり、日常的にあまり車を使わない方にとっては、ハイブリッドの強みがデメリットに変わってしまう恐れがあるのです。
維持費や修理費を抑えたい人はハイブリッド車に向いてない
「ハイブリッド車は燃費が良いから経済的」と思われがちですが、それはあくまでガソリン代の話。実際には、維持費の一部がガソリン車より高くなる可能性もあるため注意が必要です。
特に大きな負担になりやすいのが、「駆動用バッテリーの交換費用」です。
車種にもよりますが、バッテリー交換にかかる費用はおおよそ10万円〜40万円程度。これは10万km〜15万km程度の走行で必要になることもあり、想定外の出費として頭を悩ませる人も少なくありません。
また、車検時に追加のメンテナンスが必要になるケースもあります。
バッテリーの状態によっては点検費用がかさむことがあるため、「維持費をできるだけ抑えたい」という方には、あまりおすすめしづらい側面もあります。
もちろん、新車購入時に長期保証が付いている場合もありますが、それを過ぎると自己負担になる点も見逃せません。
デメリット:故障時の修理対応が特殊になる可能性
ハイブリッド車は、ガソリン車にはない「高電圧システム」や「電動モーター」「インバーター」といった専用の部品を搭載しています。これにより、万が一のトラブル時には修理が複雑になる傾向があります。
たとえば、通常の整備工場では対応できず、ディーラーや専門の技術者に依頼しなければならないことも。その場合、修理代が高額になるだけでなく、修理完了までに時間がかかるというケースも考えられます。
さらに、地方ではハイブリッド車の修理対応ができる店舗が限られている場合もあるため、緊急時のサポート体制も含めて事前に確認しておく必要があります。
日常的なメンテナンスはそれほど手間ではないものの、「いざという時の対応コストが読めない」という点では、ややハードルが高いと感じる方もいるかもしれません。
走行性能や運転の楽しさを重視する人はハイブリッド車に向いてない
車を選ぶとき、「乗り心地」や「加速感」、「走りの楽しさ」を重視する人にとっては、ハイブリッド車が少し物足りなく感じられる場面があるかもしれません。
ハイブリッド車は、エンジンとモーターの組み合わせによって走行するため、スムーズで静かな加速が得意です。しかしその一方で、アクセルを踏み込んだときの“力強さ”や“ダイレクトな反応”が弱いと感じる方もいます。
特に、スポーツタイプの車やターボ付きのガソリン車に慣れている方は、ハイブリッド車特有の「静かすぎる走り」に違和感を覚えるかもしれません。
エンジンのうなり音や、加速時の“押し出されるような感覚”が少ないため、「走っていてつまらない」と感じるケースもあるようです。
もちろん車種によってはパワフルなハイブリッドモデルもありますが、走りの“味”を楽しみたい方には、やや刺激が足りないと映ることもあるでしょう。
デメリット:独特な運転感覚
もうひとつ注意したいのが、運転中のフィーリングの違いです。
ハイブリッド車は低速時には電気モーターだけで動くことが多く、加速中にエンジンへ切り替わる際に「ガクッ」とした振動や音の変化を感じることがあります。
この切り替わりは慣れてしまえば気にならない場合もありますが、運転にこだわりがある方や“機械との一体感”を求める方には、やや違和感として残ることもあるのです。
また、回生ブレーキ(※減速時のエネルギーを電力に変えて発電する仕組み)も、一般的なブレーキとは少し感触が異なるため、慣れるまでは制動力の加減に戸惑うかもしれません。
走りの気持ちよさや、車との対話を楽しみたいという方は、購入前に一度試乗して「感覚が合うかどうか」をしっかり確認しておくことが大切です。
ハイブリッド車以外の選択肢:何を選べばいい?
ハイブリッド車以外の選択肢としてガソリン車やディーゼル車、EV(電気自動車)があげられるでしょう。
ハイブリッド車を検討する方の多くは、燃費の良さや環境への配慮にひかれたのではないかと思われます。
燃費の良さだけでいえば、ガソリン車やディーゼル車でも高性能のものがありますし、環境への配慮という点ではEVが最適でしょう。
各車両の魅力や今後の発展も含め、検討材料にできると良いですね。
ガソリン車・ディーゼル車の今後と魅力
ハイブリッド車が合わないと感じた場合、まず候補に挙がるのがガソリン車やディーゼル車です。
これらの車は、ハイブリッド車と比べて構造がシンプルで、整備費や修理費が比較的安く済む傾向があります。
特に、ガソリン車は本体価格も抑えめで選択肢も多く、維持費の予測がしやすい点が魅力です。短距離走行がメインの方や、年に数回しか車を使わない方には、かえってこちらのほうが適しているケースもあります。
一方ディーゼル車は、燃費の良さに加えてトルク(力強さ)があるため、長距離運転や荷物を多く積む用途に向いています。
特にSUVや商用車では、ディーゼルエンジンのメリットが活かされやすいですね。
ただし、都市部ではディーゼル車への規制が強化される流れもあるため、地域ごとのルールや今後の動向にも注意が必要です。
ポチモ契約でガソリン代7円引き!
EV(電気自動車)やPHEVも候補になる?
もうひとつの選択肢として注目されているのが、「EV(電気自動車)」や「PHEV(プラグインハイブリッド車)」です。
EVは完全に電気だけで走る車で、走行中のCO₂排出がゼロ。
エンジン音がなく非常に静かなことや、加速が滑らかで力強いことが特徴です。走行コストも電気代のほうがガソリンより安く済む傾向にあるため、長距離を頻繁に運転する方には向いている場合があります。
ただし、充電設備の整備や、充電にかかる時間、航続距離の制限といった課題もあり、ライフスタイルによっては不便に感じることも。自宅に充電設備を設置できない方にとっては、選びにくい選択肢かもしれません。
一方、PHEVは「ガソリンでも電気でも走れる」柔軟性を持つ車です。日常の短距離は電気で、長距離はガソリンで走るといった使い分けが可能なため、「両方の良さを取り入れたい」という方にとって魅力的な存在と言えるでしょう。
まとめ:ハイブリッド車は「万能」ではない
ハイブリッド車は、燃費の良さや環境への配慮といった魅力が多く、近年ますます注目を集めています。ですが、どんなに優れた機能を持っていても、すべての人にとって“最適な選択”とは限りません。
ハイブリッド車よりもガソリン車やディーゼル車、あるいはEVやPHEVといった他の選択肢のほうが、ライフスタイルに合っている可能性があります。
車選びで大切なのは、「流行っているかどうか」ではなく、「自分に合っているかどうか」。
見た目やスペックだけでは見えてこない部分にこそ、満足感のカギが隠れています。
後悔のない選択をするためにも、購入前に一度立ち止まって、自分の使い方や重視したい価値を見つめ直してみることをおすすめします。
人によっては、カーリースを利用するのも一つの手かもしれませんね。
カーリースでハイブリッド車に乗る選択肢について、詳細は下記の関連コラムをご覧ください。
よくあるご質問
Q
ポチモと他社の違いは何ですか?
ポチモは石油元売りの出光興産(株)が運営しているので、ご契約特典としてガソリン値引きをご提供できるのは他社にはない特徴です。ほかにも「契約終了後に必ずクルマがもらえる」「走行距離制限なし」など、マイカーのように自由にクルマをご利用いただける点もポチモの特徴といえます。
また中古車リースの場合、独自の基準を満たした高品質な車両のみを掲載し、「全車両1年保証付き」「全車両車検2年付き」「全車両にKeePerのガラスコーティング付き」という手厚いフォローもご提供しているので安心してご利用いただけます。
Q
カーリースとはどのようなものですか?
カーリースとは、クルマを長期間、賃貸契約でご利用いただくシステムです。賃貸契約ではありますが、契約期間中はマイカーのようにご利用いただけます。